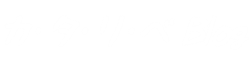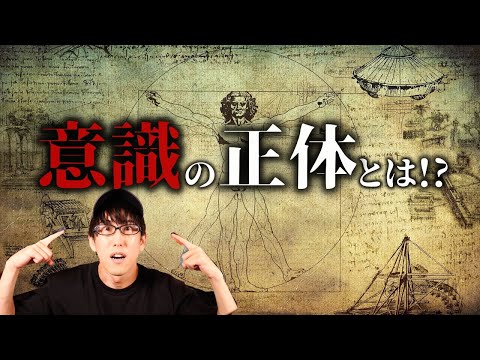You are in danger of living a life so comfortable and soft, that you will die without ever realizing your true potential.
あまりにも快適で柔らかな人生を送る危険がある。その結果、自分の真の可能性に気づかずに死んでしまう。
by デビッド・ゴギンズ
こんにちは。当ブログへのご訪問ありがとうございます。
「今年こそは、酒をやめるぞ!」
「タバコも、もう潮時だよな…」
新年や誕生日、健康診断の結果が出たタイミングで、誰もが一度はそう誓ったことがあるんじゃないでしょうか。
でも、現実は厳しい(笑)。
気づけばまた同じ場所に逆戻り…なんて経験、僕も死ぬほどしてきました。
今回は、そんな「やめたいのにやめられない」悪習慣に本気で終止符を打ちたいと思っている人に向けて、僕自身が10年以上の断酒・断煙を継続できている、その核心部分について話そうと思います。
結論から言うと、気合や根性だけじゃ絶対に無理です。
大事なのは、脳の仕組みを理解して、マインドセットを根本から変えること。
つまり、「~しなければならない(have to)」という義務感から、「~したい(want to)」という心からの願望へ、どうやってシフトさせるか。これが全てです。
- 多くの人が禁酒・禁煙に失敗する本当の理由
- 「have to」と「want to」のモチベーションの決定的違い
- 脳の仕組みを利用した悪習慣を断ち切る科学的アプローチ
- 僕が15年間実践している瞑想やアファメーションの効果
- 今日から始められる具体的な3つのステップ
>>あなたという習慣を断つ ― 脳科学が教える新しい自分になる方法
なぜあなたの禁酒・禁煙は失敗するのか?悪習慣を断つ方法の落とし穴
- 「禁止」が逆効果になる心理的メカニズム
- 「have to(義務)」と「want to(願望)」の決定的な違い
- 悪習慣の強力なループと脳の仕組み
多くの人が「断酒」や「断煙」といった悪習慣を断つ方法に挑戦して、そして挫折していきます。
僕も昔はそうでした。
洋服屋を潰して、妻の父親の工場で働きながら月5,000円のお小遣いで生活していた頃なんて、本当にクソみたいな人生でした(笑)。
酒とタバコに溺れ、現実から逃げる毎日。
「このままじゃダメだ」と頭では分かっているのに、どうしてもやめられない。
この章では、なぜ僕達の固い決意が、いとも簡単に崩れ去ってしまうのか、その根本的な原因を深掘りしていきます。
それは根性が足りないからでも、意志が弱いからでもありません。
実は、人間の心理や脳の仕組みに、その答えが隠されています。
このメカニズムを理解することが、無限ループから抜け出すための最初の、そして最も重要な一歩になります。
「禁止」が逆効果になる心理的メカニズム
「タバコを吸ってはダメだ」「酒を飲んではいけない」。
こうやって自分に「禁止」を課すことから始める人、めちゃくちゃ多いですよね。
でも、残念ながら、それは逆効果になることがほとんどです。
これは心理学でいう「カリギュラ効果」というやつで、人は禁止されればされるほど、その行為をしてみたくなるっていう厄介な性質を持っています。
「絶対に押すなよ!」と言われると、つい押したくなるあの有名なボタンと同じ理屈です(笑)。
自分自身に「禁止」という強い命令を下すことは、脳に「酒」や「タバコ」のことを四六時中考えさせるようなもの。
例えるなら、ダイエット中に「ケーキのことだけは絶対に考えるな!」と自分に言い聞かせているようなものです。
結果、どうなるか?
頭の中はケーキのことでいっぱいになり、普段より何倍も食べたくなってしまう。
それと同じで、「禁酒」「禁煙」という言葉を使えば使うほど、僕達の脳はそれに執着し、かえって欲求を増大させてしまうんです。
だから、そもそもアプローチが間違っている。
「禁止」で自分を縛り付けるのではなく、もっと賢いやり方で脳を味方につける必要があるんです。
「have to(義務)」と「want to(願望)」の決定的な違い
次に、モチベーションの質についてです。
ここが今回の記事で一番伝えたい核心部分かもしれません。
悪習慣を断とうとするとき、多くの人が抱くのは「~しなければいけない(have to)」という義務感です。
「健康のために、酒をやめなければいけない」
「家族のために、タバコをやめなければいけない」
一見すると、これは正しい動機のように思えます。
でも、「have to」のモチベーションは、実はめちゃくちゃ脆いんです。
なぜなら、それは常に「我慢」や「苦痛」を伴うからです。
人間の脳は本能的に苦痛を避けるようにできていますから、「have to」で何かを続けようとするのは、言うなれば、アクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるような状態。
そりゃあ、いつかガス欠になるに決まってます。
一方で、「~したい(want to)」という願望から来るモチベーションは、全く性質が異なります。
「もっと健康になって、エネルギッシュな毎日を送りたい!」
「思考をクリアにして、仕事のパフォーマンスを最高にしたい!」
これは、我慢ではなく「喜び」や「興奮」を伴う動機です。
脳が喜ぶことだから、誰かに言われなくても勝手にやりたくなる。
この「have to」から「want to」へ、どうやってマインドを切り替えるか。
悪習慣を断つ方法は、ここに全てが集約されていると言っても過言ではありません。
悪習慣の強力なループと脳の仕組み
そもそも、なぜ僕達は一度ハマると悪習慣から抜け出せなくなるんでしょうか。
それは、脳の中に「習慣ループ」と呼ばれる強力な回路が出来上がってしまうからです。
これは「きっかけ→ルーチン→報酬」という3つの要素で構成されています。
例えば、喫煙者の場合だと…
- きっかけ:仕事でストレスを感じる、食後の一服
- ルーチン:タバコに火をつけて吸う
- 報酬:ニコチンによる一時的なリラックス感、満足感
このループが何度も繰り返されることで、脳の神経回路はどんどん強化されていきます。
そうなると、もはや意志の力だけでこの流れに逆らうのは、ほとんど不可能。
それはまるで、毎日同じ道を通ってできた深いくぼみ(轍)のようなもので、意識しなくても勝手にタイヤがそっちに流れていってしまうんです。
だから、「気合で我慢する!」というアプローチは、深い轍にハマった車を力ずくで引き上げようとするようなもので、無駄なエネルギーを消費するだけで、すぐに疲弊してしまう。
重要なのは、このループの仕組みを理解した上で、力ずくで戦うのではなく、新しい別の道(新しい習慣)を作ってあげることなんです。
マインドを変える断酒・断煙|悪習慣を断つ方法の核心
- 「やめる」のではなく「新しい自分になる」と決意する
- 脳の門番「RASの法則」を味方につける具体的な方法
- 僕が15年続ける瞑想とアファメーションの科学的な力
前の章で、気合や根性論がいかに無力であるか、そして「have to」のモチベーションがいかに脆いかを話しました。
じゃあ、具体的にどうすればいいのか?
ここからが本題です。
悪習慣を断つ方法の核心は、テクニックや小手先の技じゃありません。
全ては「マインド」から始まります。
僕自身が月5,000円のお小遣い生活から抜け出し、法人設立まで至ることができたのも、アフィリエイトのスキルを学んだことはもちろんですが、その根底にはマインドセットの根本的な変革がありました。
この章では、そのマインドセットを「have to」から「want to」へ切り替えるための、脳科学に基づいた具体的な方法を解説していきます。
これは、断酒や断煙だけでなく、人生のあらゆる場面で応用できる、めちゃくちゃ強力な考え方です。
「やめる」のではなく「新しい自分になる」と決意する
まず、言葉の定義から変えていきましょう。
僕は「禁酒」「禁煙」という言葉を使いません。
必ず「断酒」「断煙」と言います。
「禁」という字には、「禁止する」「我慢する」というネガティブなニュアンスがどうしても付きまといます。
これは、前の章で話した「have to」の世界観そのものです。
一方、「断」という字は、「断ち切る」「決別する」という、より能動的でポジティブな意志を感じさせます。
これは単なる言葉遊びではありません。この動画でも「禁酒ではなく、断酒という言葉にこだわる」ということを言われています。
言葉は思考を作り、思考は現実を作ります。
だから、「酒をやめる」「タバコをやめる」という発想自体を、一度ゴミ箱に捨ててみてください。
代わりに、「酒やタバコに頼らない、新しい自分に生まれ変わる」と決意するんです。
これは、何かを「失う」というネガティブな行為ではなく、新しい価値を「得る」というポジティブな創造行為です。
「酒を飲めない可哀想な自分」ではなく、「クリアな思考と健康な肉体を手に入れたカッコいい自分」という新しいセルフイメージを構築する。
このマインドセットの転換こそが、全ての始まりです。
心理学でいう「信念のリランキング」に近い考え方かもしれません。
「酒が飲めない辛さ」という価値観よりも、「健康でいられる喜び」という、より上位の価値観に焦点を合わせることで、行動の優先順位を自然に変えていくアプローチです。
脳の門番「RASの法則」を味方につける具体的な方法
「新しい自分になる」と決めたら、次にそのイメージを脳に定着させる必要があります。
ここで登場するのが、僕がスピリチュアルや引き寄せの法則のアンチテーゼとして重視している「RAS(網様体賦活系)」の法則です。
難しそうな名前ですが、要は「脳の優秀な門番」のこと。
僕達の脳には毎秒4億ビットというとんでもない量の情報が流れ込んでいますが、意識的に処理できるのは、そのうちのたった2,000ビット程度だと言われています。
RASは、その膨大な情報の中から「自分にとって重要な情報」だけを選び出して、意識に届けてくれるフィルターの役割を担っています。
これ、身近な例で説明するとめちゃくちゃ分かりやすいです。
- 「赤い車が欲しいな」と思った途端、街中でやたらと赤い車が目につくようになる。
- 自分が妊娠したり、パートナーが妊娠したりすると、急に妊婦さんやベビーカーが目に付くようになる。
- 騒がしいパーティ会場でも、自分の名前が呼ばれるとハッキリ聞こえる(カクテルパーティー効果)。
車の数や妊婦さんの数が実際に増えたわけじゃありませんよね(笑)。
RASが「赤い車」や「妊婦さん」に重要フラグを立てたから、それらの情報が優先的に意識に上るようになっただけなんです。
この仕組みを、悪習慣を断つために意図的に利用します。
つまり、「酒やタバコのない人生の素晴らしさ」に関する情報に、RASの重要フラグを立てさせるんです。
具体的には、「自分はエネルギッシュで健康的な人間だ」と繰り返し自分に言い聞かせたり(アファメーション)、そういう理想の自分を鮮明にイメージしたり(ビジュアライゼーション)します。
そうすると、RASは「エネルギッシュ」「健康的」に関連する情報を自動的に集め始めます。
例えば、健康的な食事のレシピが目に留まったり、ランニングしている人が輝いて見えたり、逆に酒やタバコの害に関するニュースがやたらと気になったり。
こうして脳が勝手に「want to」の世界観を補強する情報を集めてくれるようになるんです。
詳しくは以前書いた【マーフィーの法則】厄年、思い込み、錯覚、プラセボ、は全てが脳のRASの仕組みという記事も参考にしてみてください。
僕が15年続ける瞑想とアファメーションの科学的な力
RASを効果的に機能させる上で、僕が絶対に欠かせないと考えているのが「瞑想」と「アファメーション」です。
僕が瞑想を始めたのは2008年頃、独立する前で、藁にもすがる思いで引き寄せの法則に興味を持ったのがキッカケでした。
でも、続けていくうちに、これはスピリチュアルな話ではなく、完全に脳科学的な「脳の筋トレ」なんだと理解しました。
瞑想は、ごちゃごちゃになった頭の中(思考のガレージ)を整理整頓し、クリアな状態を保つためのトレーニングです。
思考が整理されると、自分が本当に望んでいること(want to)が明確になります。
そして、そのクリアになった脳に、アファメーション(肯定的自己暗示)によって「自分はこうである」という新しいプログラムをインストールしていくんです。
「私は、毎日を健康でエネルギッシュに過ごす人間だ」
「私は、クリアな思考で最高のパフォーマンスを発揮する」
これを毎日繰り返すことで、潜在意識レベルでセルフイメージを書き換えていく。
これは、心理学でいう「コミットメントと一貫性」の原理にも繋がります。
一度「自分はこういう人間だ」と公言(自分自身に対して)すると、そのイメージと一貫した行動を取り続けようとする心理が働くんです。
僕はこの心のトレーニングを「保険」と同じだと考えています。
体の変化は体重計や鏡で分かりますが、心の負担や変化は、壊れるその瞬間まで分かりません。
そして、壊れてから慌てて心のトレーニングを始めても遅いんです。
だからこそ、何もない平穏な時にこそ、万が一の「来てほしくないその時」のために、瞑想とアファメーションで心を鍛え続ける必要があるんです。
この辺りの話はChatGPTが優秀過ぎて瞑想の概念が変わった話でも詳しく書いているので、良かったら読んでみてください。
凡人だった僕が実践した、悪習慣を断つ方法の3ステップ
- STEP1: まずは「敵」と「味方」を徹底的に知る
- STEP2: 物理的に距離を取る「環境」の作り方
- STEP3: 新しい「快楽」で脳を上書きする技術
さて、マインドセットの重要性について散々語ってきましたが、もちろん精神論だけでは不十分です(笑)。
「want to」の気持ちを高めた上で、具体的な行動に移していく必要があります。
僕自身、特別な才能があったわけではありません。
むしろ、意志が弱く、流されやすい、どこにでもいる凡人でした。
そんな僕でも継続できている、誰にでも再現可能な具体的な3つのステップを紹介します。
これは、前章で解説した脳の「習慣ループ」を意識した、非常に実践的なアプローチです。
難しいことは何一つないので、ぜひ今日から試してみてください。
STEP1: まずは「敵」と「味方」を徹底的に知る
孫子の兵法にも「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とありますが、これは悪習慣との戦いでも全く同じです。
まずは、自分が断ち切りたい悪習慣(敵)について、徹底的に調べることから始めます。
例えば、アルコールやニコチンが、具体的にどのように脳や身体に作用し、依存させていくのか。
その害はどれほどのものなのか。
逆に、それらを断つことで、どれだけ素晴らしいメリット(味方)が得られるのか。
・睡眠の質が劇的に向上する
・肌がきれいになる
・思考がクリアになり、集中力が上がる
・お金が貯まる
・自己肯定感が上がる
こういった情報を、本やYouTube、信頼できるウェブサイトなどで、嫌というほどインプットしてください。
これは、脳に対して「悪習慣=苦痛」「断つこと=快楽」という新しい方程式を刷り込むための重要なプロセスです。
知識は、感情をコントロールするための強力な武器になります。
漠然とした「やめなきゃ」ではなく、「こんな毒物を体内に入れるなんて、アホらしい」「こんなメリットがあるなら、やらない方が損だ」と、心の底から思えるレベルまで、知識で自分を武装するんです。
この「知る」という行為が、後のステップ全ての土台になります。
STEP2: 物理的に距離を取る「環境」の作り方
マインドと知識で武装したら、次は物理的な環境を整えます。
意志の力なんて、環境の前では無力です。
これは断言できます。
家に酒やタバコが置いてある状態で我慢しようとするのは、例えるなら、地雷原のど真ん中で「絶対に地雷を踏まないように気をつけよう」と言っているようなもの。
めちゃくちゃ危険で、非効率です(笑)。
一番確実なのは、地雷原から出て行くこと、つまり物理的に悪習慣の原因を生活から排除することです。
- 家にある酒、タバコ、灰皿などを全て処分する。
- 飲み会や喫煙所など、悪習慣の「きっかけ」となる場所や集まりには、最初のうちは絶対に行かない。
- コンビニに行ったら、酒・タバココーナーには目を向けない。
「付き合いが悪いと思われるかも…」と心配になるかもしれません。
でも、本気で自分を変えたいなら、一時的に失う人間関係を恐れてはいけません。
本当に大切な人なら、あなたの決意を理解し、応援してくれるはずです。
環境が人間を作ります。
自分の意志力を過信せず、自分が誘惑に負けようがない「仕組み」・「環境」を強制的に作り出すことが、成功への最短ルートです。
STEP3: 新しい「快楽」で脳を上書きする技術
悪習慣のループは「きっかけ→ルーチン→報酬」で成り立っていると話しました。
STEP2で「きっかけ」を物理的に排除しましたが、それでも長年染み付いた欲求は、ふとした瞬間に顔を出します。
「あー、一杯やりたいな」「一服したいな」
この欲求が生まれたときに、それを我慢するのではなく、別の行動で「報酬」を与え、習慣を上書きしていくのがこのステップです。
重要なのは、元の悪習慣で得られていた「報酬」に近い、あるいはそれ以上の「快楽」を脳に与えること。
例えば、僕の場合はこうでした。
- 酒が飲みたい(ストレス解消したい)と思ったら → 強炭酸水を飲む、熱いシャワーを浴びる、キックボクシングのジムで汗を流す。
- タバコが吸いたい(一息つきたい)と思ったら → 深呼吸をする、ガムを噛む、好きな音楽を1曲だけ集中して聴く。
ポイントは、手軽にできて、即座にスッキリするような代替行動をいくつか用意しておくこと。
これを繰り返すことで、脳は「ストレスを感じたら→強炭酸水を飲む→スッキリする」という新しい習慣ループを学習し始めます。
古い轍(わだち)の横に、新しい快適な道ができていくイメージです。
時間が経つにつれて、脳はより簡単で気持ちいい方の新しい道を、自然と選ぶようになっていきます。
これが、我慢に頼らない習慣の上書きテクニックです。
これで挫折しない!断酒・断煙で悩む人が悪習慣を断つ方法
- 「1ミリでも進めばOK」完璧主義を捨てる勇気
- モチベーションが上がる本や動画の紹介
- 「健康は当たり前じゃない」という感謝の気持ちの重要性
マインドセットを変え、具体的なステップを踏み出しても、長い道のりの途中では、必ず壁にぶつかったり、心が折れそうになったりする瞬間が訪れます。
特に最初の3ヶ月は、禁断症状との戦いもあり、一番の踏ん張りどころです。
この最後の章では、そうした困難な時期を乗り越え、断酒・断煙を継続していくために、僕自身が大切にしている考え方や、支えになったツールを紹介します。
悪習慣を断つ方法は、短期決戦のスプリントではなく、長期的なマラソンです。
最後まで走り切るための、心の給水所だと思って読んでみてください。
「1ミリでも進めばOK」完璧主義を捨てる勇気
何か新しいことを始めるとき、僕達はつい完璧を目指してしまいがちです。
「一度も吸わないぞ!」「一滴も飲まないぞ!」と高い目標を掲げる。
もちろん、その意気込みは素晴らしい。
でも、その完璧主義が、挫折の最大の原因になることもあります。
一度でも失敗してしまうと、「ああ、もうダメだ」と全てを投げ出してしまい、リバウンドしてしまうんです。
大事なのは、完璧であることよりも、歩みを止めないことです。
たとえ昨日より1ミリでも前に進んでいれば、それは立派な前進です。
もし、誘惑に負けてしまったとしても、自分を責めないでください。
「まあ、人間だもの、そういう日もあるさ(笑)。でも、明日からまた切り替えよう」
このくらいの軽やかさが必要です。
石橋を叩きすぎて壊してしまうくらいなら、多少グラついても渡り切ってしまう方がいい。
0か100かで考えるのではなく、1でも2でも前に進んでいる自分を認め、褒めてあげること。
この自己肯定こそが、長いマラソンを走り抜くための、一番のエネルギー源になります。
モチベーションが上がる本や動画の紹介
自分一人の力だけで戦い続けるのは、正直しんどい時もあります。
そんな時は、外部からの刺激をうまく活用するのもめちゃくちゃ有効です。
僕自身、何度も本や動画の言葉に救われ、モチベーションを再燃させてきました。
ここで、僕が特に影響を受けたものをいくつか紹介します。
デビッド・ゴギンズの言葉
元米海軍特殊部隊SEALs隊員であるデビッド・ゴギンズ。
彼の言葉は、まさに「魂の渇入れ」です(笑)。
「快適な場所は、夢が死ぬ場所だ」「苦しみは成長の代償である」
彼の哲学は、自分の限界を突破し、安楽な道から抜け出すための強烈な動機付けを与えてくれます。
YouTubeで彼のスピーチ動画がたくさん見つかるので、心が弱っている時に観ると、強制的にスイッチが入るのでオススメです。
特にこの記事を書くにあたって参考にした動画は、心が折れそうな時に見てみてください。
ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣
この本は、習慣化に関する科学的なアプローチを、これでもかというくらい分かりやすく解説してくれています。
僕がこの記事で話してきた「習慣ループ」や「環境設定の重要性」なども、この本から多くの示唆を得ました。
根性論ではなく、具体的なシステムとして習慣をどうデザインしていくか。
悪習慣を断つだけでなく、良い習慣を身につけたい全ての人にとってのバイブルだと思います。
「健康は当たり前じゃない」という感謝の気持ちの重要性
最後に、僕が断酒・断煙を続ける上で、最も根底にあるマインドについて話します。
それは、「健康は当たり前ではない」という、当たり前の事実に対する感謝の気持ちです。
若い頃は、健康なんて空気みたいなもので、そのありがたみなんて考えたこともありませんでした。
でも、50代にもなると、周りでも体調を崩す人が増えてきますし、自分自身の体の変化も感じます。
今の僕にとって、「健康こそ全て!自分を大事にしよう!」というのが一番の人生の目標です。
この感覚は、失って初めて分かるものかもしれません。
でも、失う前に気づけたなら、それに越したことはない。
酒やタバコで自分の体を意図的に傷つける行為は、将来の自分から「健康」というかけがえのない資本を前借りしているようなものです。
そう考えると、「飲みたい」「吸いたい」という一瞬の快楽のために、将来の大きな幸せを犠牲にするのが、いかに馬鹿げたことか、心の底から理解できるはずです。
毎朝、目が覚めて、痛みもなく、普通に呼吸ができて、自分の足で歩ける。
この奇跡に感謝する気持ちを持つこと。
このマインドが、「want to」のモチベーションを支える、最も深く、最も強力な土台になってくれると僕は信じています。
このあたりの心境は【酒とタバコ】健康こそ全て!自分を大事にしよう!が今の1番の人生の目標という記事にも書いているので、よければぜひ。
まとめ:断酒・断煙で悩んでる人へ。悪習慣を断つ方法はマインドが9割
ここまで、僕が実践してきた断酒・断煙、そして悪習慣を断つ方法について、マインドセットを中心に話してきました。
何度も言いますが、小手先のテクニックや根性論では、長年連れ添った悪習慣という強敵には太刀打ちできません。
大事なのは、脳と心の仕組みを理解し、それを逆手にとって自分を導くこと。
「~しなければならない」という苦痛の道ではなく、「こうなりたい!」という希望の道を、自分自身で作り出すこと。
そのための武器は、知識であり、マインドセットであり、そして日々の小さな実践です。
この道は、決して楽な道ではありません。
でも、その先には、過去の自分では想像もできなかったような、クリアで、エネルギッシュで、自己肯定感に満ちた素晴らしい世界が待っています。
僕のような凡人でもできたんですから、これを読んでいるあなたにできないはずがありません。
この記事が、あなたの新しい一歩を踏み出すキッカケになれば、めちゃくちゃ嬉しいです。
- 悪習慣を断つには気合や根性論だけでは失敗する
- 「禁止」はカリギュラ効果で逆効果になる可能性が高い
- 「have to(義務)」ではなく「want to(願望)」のモチベーションが重要
- 脳の習慣ループを理解し力ずくで戦わないこと
- 「やめる」のではなく「新しい自分になる」というマインドセットを持つ
- 脳のフィルター機能であるRASの法則を味方につける
- 瞑想とアファメーションは科学的な脳の筋トレである
- 具体的なステップとして知識武装・環境設定・習慣の上書きが有効
- 完璧を目指さず歩みを止めないことが継続のコツ
- 健康であるという奇跡に感謝する気持ちが最強の土台となる